まだ1つしかしか知らないの?DESC法・PREP法・SDS法。あなた以外みんな使ってるプレゼンのキホン
プレゼンやブログ・面接で知らないと損をする3つのテクニック、DESC法、PREP法、SDS法の違いを具体例を比べながら解説します。
目次
はじめに

DESC法、PREP法、SDS法とちょっと覚えにくい名前ですが、共通することは「文章やプレゼンの構成の分け方」です。
言いたいことだけを伝えても相手の頭には入らない
言いたいことをそのまま伝えても相手の頭には入りません。その情報を受け入れる「箱」が用意されていないからです。
例えばいきなり

部下
この設備を買いましょう1000万円です
と上司に言っても、相手からすると

上司
何を言ってるんだ
となるのです。
言いたいことの前に、相手の頭に、それを受け入れる場所を作り上手くその「箱」に伝えたいことを入れること。これがDESC法、PREP法、SDS法の共通の考え方です。
まずはそれぞれの内容を見ていきましょう。

せつやくん
どれも英語の頭文字の組み合わせなのでそれを意識して覚えましょう。
DESC(Describe Express Suggest Consequence)法

Describe(描写)
Describe(描写)、状況を客観的に描写します。(例: 自動車のスマホよそ見運転による事故が年々増加してきています。)
Express(表現)
Express(表現)、主観的な意見や問題点を表現します。(例:このままではさらに情報端末が普及した5年後には事故件数は今の倍に増加します。)
Suggest(提案)
Suggest(提案)、上記に対する解決法を提案します。(例:そこで新車への自動運転機能の搭載を義務化することを提案します。)
Consequence(結果)
Consequence(結果)、上の提案によりどのような結果になるかを述べます。(例:これにより事故件数は5年後で現在の半分になることが期待できます。)
DESC法の特徴と事例
DESC法は3番目の「提案」が本当に伝えたいことですが、なぜそうする必要があるのかを「背景」から「問題点」へと順序立てて説明します。
そして、「提案」ののち、そうしたらどうなるのかを最後の「結果」として表します。
DESC法は何らかの問題点とそれに対する提案を伝えるための技術です。そしてその問題点をいきなり伝える前に背景を表すことでその問題点が客観的にも正しいこと、そしてその問題点を入れる「箱」を相手の頭の中に用意するのです。

せつやくん
DESC法は主に誰かに承認を貰う時に主に使うテクニックです。
PREP(Point Reason Example Point)法

Point(要点)
Point(要点)、ポイントを簡潔に伝えます。(例:この車はあなたの時間を増やします。)
Reason(理由)
Reason(理由)、上のポイントについて「なぜか」を詳しく説明します。(例:なぜならこの車には新機能である自動運転装置がついているからです。)
Example(例)
Example(例)、具体的な例をあげます(例: 自動的運転の間、あなたは本を読んだりゲームをしたりと好きな事ができます。)
Point(再び要点)
Point(再び要点)、ポイントを言葉を変えて復唱します。(例:この車はあなたの好きな事ができる時間を増やします。)
PREP法の特徴
PREP法はまず最初に「要点」を伝えます。相手の頭の中にハテナ?の「箱」を作るのです。人は疑問を持つと情報を自ら受け入れようとします。
そしてそのハテナに対して2番目に「理由」を伝えるのです。理由というのは理論のようなものでそれだけでは理解しづらいもの。そこですかさず3番目に「具体例」を挙げます。
つまり相手の頭の中にハテナを連鎖させるのです。そして最後に再び最初の「要点を復唱」します。これでハテナの連鎖が解決して見事相手の頭に情報がはまりこむという訳です。

せつやくん
PREP法は人に何かを教えたい時に使います。教本やセミナーなどに特に有効です。
SDS(Summary Detail Summary)法
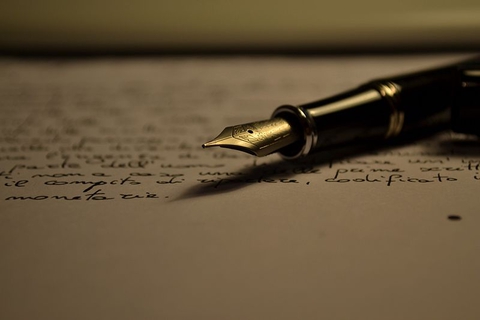
Summary(要約)
Summary(要約)、要約を短く伝えます。(例:この車にはあなたのカーライフから3つの無駄を省く機能があります。)
Detail(詳細)
Detail(詳細)、上の要約についてより詳しく伝えます。(例:それは運転しなくてもよい自動運転機能、ガソリンを入れなくても走れる無燃料走行機能、道が無くても進める飛行機能です。)
Summary(再び要約)
Summary(再び要約)、 再び要約を言葉を変えて復唱します。(例:これらの3つの機能はあなたのカーライフを最適化します。)
SDS法の特徴
SDS法は一番汎用的に使えシンプル、かつ強力な伝達方法です。構成も非常に簡単。「要約」を伝えてから「詳細」を、そしてまた「要約」を伝えるだけです。
本当に伝えたいことはもちろん「詳細」の部分ですが、いきなり長く話すと相手は「頭の中にどんな大きさの箱を用意したらいいのか」がわからず混乱してしまいます。
最初に要約を伝えることで、大体の情報量をイメージすることができ、ペースを掴みながら詳細を聞けるという訳です。
そして詳細の後に再び要約を聞くことで、相手は先に聞いた詳細を頭の中で思い出しまとめ上げ、「記憶」を作り上げます。
本を読む時にまず目次を眺めてから内容を、そして最後に目次を読み返すことで理解しやすいのと同じですね。

せつやくん
SDS法は目的を選ばずに使用できる便利なテクニックです。例えば日記や報告などでも活用できます。
目的によるDESC法、PREP法、SDS法の使い分け

ということで最後に伝達の3つのテクニック、DESC法・PREF法・SDS法の用途をまとめます。
| 伝達方法 | 主な用途 |
|---|---|
| DESC法 | 人に何かを承認させたい時 |
| PREP法 | 人に何かを教えたい時 |
| SDS法 | 目的を選ばずに使用可能 |
DESC法は人に何かを承認させたい時に使います。問題点を提起してから解決法を伝える事でより提案力が増します。企画資料や提案などに特に有効です。
PREP法は人に何かを教えたい時に使います。要点の他に説明と例をまじえる事でより理解が深まります。教本やセミナーなどの教育的な表現をする時に特に有効です。
SDS法は汎用的です。PREP法やDESC法が使えない場面でも目的を選ばずに使用できます。例えば日記や報告などでも活用できます。

せつやくん
それぞれは似ていますが述べたい目的により使い分けることが重要です。